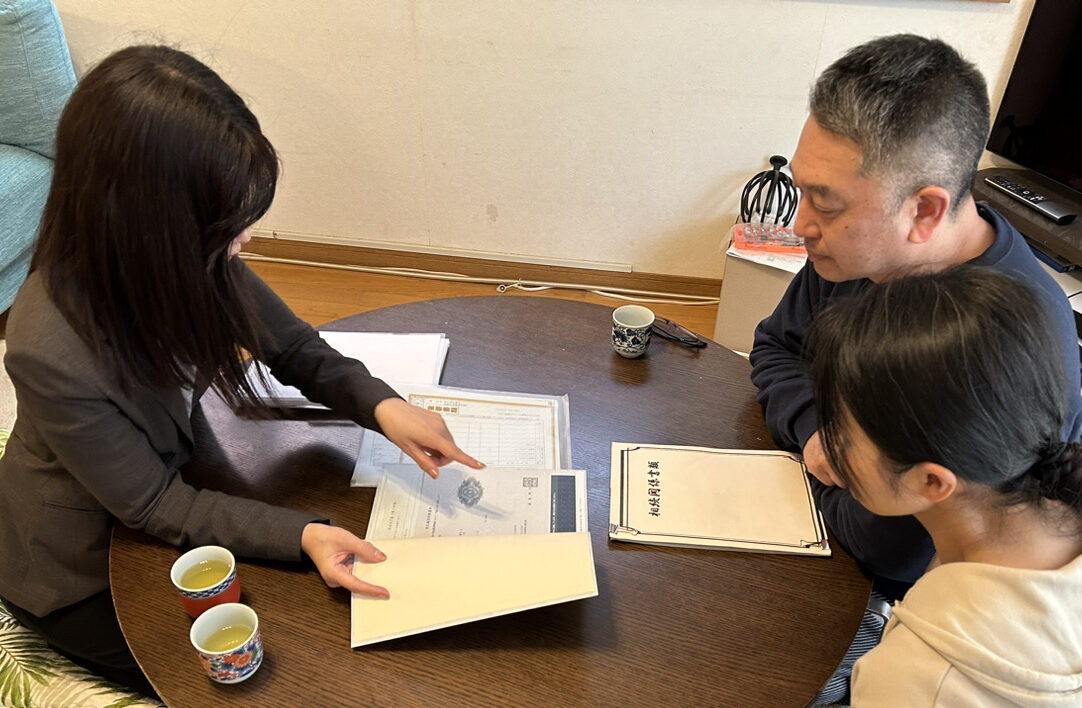
あいち相続ひろばの野々山です。
相続手続で不動産を共有名義にするかどうか悩んでいませんか。特に複数の相続人が関わる場合、共有名義は一見便利に思えますが、将来の売却や賃貸、担保設定に制限がかかることや、相続人間の合意形成が難しくなるリスクがあります。
本記事では、相続登記で共有名義にする際に知っておきたいリスクや具体的な事例、回避するための分割方法、専門家に相談するタイミングまで丁寧に解説します。読むことで、共有名義のメリット・デメリットを理解し、安全で円滑な相続手続を進める方法がわかります。
この記事は、実家や自宅の土地・建物を相続予定で、相続人間のトラブルや手続きの複雑化を避けたい中高年女性をターゲットにしています。初めて相続登記を行う方でも理解しやすい内容になっています。
前編では、相続登記で不動産を共有名義にすると売却・賃貸・担保設定の制約や相続人間のトラブルが起こりやすいことを解説しました。ここでは、共有名義を避けつつ、相続手続きを円滑に進める方法や分割手段を具体例とともにご紹介します。
相続手続では、不動産を**「現物分割」「代償分割」「換価分割」**などの方法で分けることができます。各方法にはメリットと注意点があります。
不動産そのものを相続人ごとに分ける方法です。例えば、土地を複数の区画に分けて兄は北側、妹は南側を取得する場合です。
メリット
各相続人が単独で所有するため、売却や賃貸など自由度が高い
管理や使用方法の合意が不要
注意点
不動産の形状や規模によっては分割が難しい
道路付けや法規制の制約で分割できない場合がある
特定の相続人が不動産を取得し、他の相続人には金銭で代償を支払う方法です。例えば、自宅を長男が取得し、妹や次男には現金で相続分を渡す場合です。
メリット
共有名義を避けつつ公平な分配が可能
将来的なトラブルのリスクが低い
注意点
代償金の資金調達が必要
相続税や譲渡税の負担計算を慎重に行う必要がある
不動産を売却して現金化し、相続人間で分配する方法です。
メリット
共有状態を避け、平等に分配できる
不動産管理や維持コストの負担が不要
注意点
売却価格が想定より低い場合がある
売却手続きや仲介手数料が発生する
相続人間でトラブルを避けるためには、以下の点を意識すると安心です。
不動産の評価を正確に把握する
相続税申告や公平な分配のためには、不動産鑑定士や税理士に相談し、時価を確認することが重要です。
相続人間で事前に話し合う
分割方法や取得希望、代償金の額について、早い段階で合意形成を図ることでトラブルを未然に防げます。
書面で記録を残す
協議内容や合意事項は遺産分割協議書にまとめ、全員署名押印することで、後々の紛争リスクを下げられます。
専門家の関与を検討する
司法書士や行政書士が手続きの代理や書類作成を行い、不動産鑑定士が評価を担うことで、公平性と正確性を確保できます。
例1:代償分割でトラブル回避
母から相続した自宅を長男が取得し、妹と次男には現金で代償分割。代償金の額は不動産鑑定士の評価をもとに算定。結果、共有名義にせず、売却や管理の問題を回避。
例2:換価分割で公平に分配
複数の賃貸マンションを売却して現金化。相続人間で分配することで、共有状態による家賃収入や管理費の揉め事を防止。
例3:現物分割の難しさ
不整形な土地を現物分割しようとしたが、分割が困難で結果的に代償分割に切り替え、全員納得の形で手続き完了。
司法書士:相続登記手続きや書類作成の代理
税理士:相続税計算、納付計画の立案
不動産鑑定士:適正な不動産評価、代償金算定の根拠作成
これらの専門家が連携することで、共有名義による制約やトラブルを未然に防ぎつつ、相続手続をスムーズに進めることができます。
共有名義のリスクを避けるには、現物分割・代償分割・換価分割などの方法を検討することが重要です。相続人間での合意形成や専門家の関与により、トラブルを未然に防ぎ、売却や管理の自由度を確保できます。
次の後編では、共有名義にしてしまった場合のリスク対策や解消方法、手続きの流れについて詳しく解説します。
関連記事
相続ってまずは何から・・・?
土地・建物の名義変更で失敗しないための手続きガイド|登記義務化・費用・必要書類を徹底解説③
【決定版】名古屋で土地の名義変更をお考えの方へ|相続登記から費用・手続きまでわかる完全ガイド①【あいち相続ひろば】