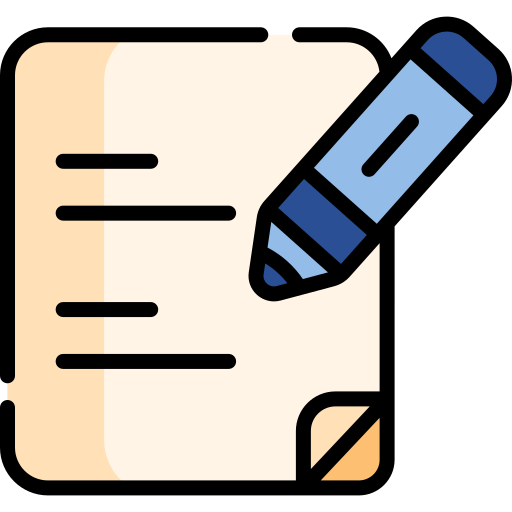
あいち相続ひろばの野々山です。
「遺言書が見つかったけれど、どのように相続手続きを進めればよいのか分からない」「遺言書の内容に従って不動産や預貯金の名義を変更したい」と悩んでいませんか。相続手続は、遺言の有無によって進め方が大きく変わり、専門知識がないまま進めると手続きの遅れや相続トラブルにつながることがあります。
本記事では、遺言書がある場合の相続手続の具体的な流れをわかりやすく解説します。遺言の種類、必要書類、司法書士や税理士との連携方法、注意点まで網羅しています。この記事を読むことで、手続きをスムーズに進めるための知識が身につき、安心して相続手続を進めることができます。特に、50〜70代で実家や自宅を相続予定の方、初めて遺言書に関わる方に向けた内容です。
遺言書は、相続手続をスムーズに進める上で非常に重要な役割を果たします。しかし、遺言の種類によって手続きの方法や必要書類が異なるため、まずは種類と法的効力を理解することが大切です。主に次の3種類があります。
自筆証書遺言
遺言者本人が全文を手書きで作成する形式です。日付と署名が必須で、財産目録はパソコンで作成しても構いません。2020年からは法務局で保管できる制度が始まり、検認手続きが不要になりました。
公正証書遺言
公証人役場で作成する形式で、遺言者と証人2名が立会い、内容が公文書として記録されます。法的に確実な形式であり、紛失や偽造のリスクがほぼありません。
秘密証書遺言
内容は非公開で作成し、公証人の認証を受けます。秘密性を重視する方に向いていますが、手続きがやや複雑です。
ポイント: 遺言の種類に応じて、相続手続での書類提出や家庭裁判所の検認の必要性が変わります。特に自筆証書遺言は、検認を経てから手続きを進める必要があるため、早めに確認することが重要です。
遺言書がある場合の相続手続は、法定相続人全員の合意が不要で、原則として遺言書の内容に従って進めます。基本的な流れは以下の通りです。
遺言書の確認
日付、署名、押印の有無、法的効力を確認します。自筆証書遺言は家庭裁判所での検認が必要ですが、法務局で保管されている場合は不要です。
相続人の確認
戸籍謄本や除籍謄本を取得し、法定相続人を確定させます。ここで漏れがあると手続きが止まるため注意が必要です。
遺産目録の作成
不動産、預貯金、有価証券、保険などすべての財産を一覧にして整理します。特に不動産は登記簿の確認も忘れずに行いましょう。
不動産の名義変更(登記)
遺言書に基づき、不動産登記簿の名義を変更します。司法書士に依頼することで、書類不備や手戻りのリスクを防ぎ、短期間で手続きが完了します。
預貯金や株式の名義変更
金融機関や証券会社に必要書類を提出します。遺言書の原本、相続人の印鑑証明書、戸籍謄本などが必要です。
相続税申告(必要な場合)
遺産総額が基礎控除を超える場合、税理士と連携して相続税申告を行います。期限は相続開始から10か月以内です。
自筆証書遺言は検認が必要
法務局保管の場合は不要ですが、自宅で保管されている場合は家庭裁判所で検認を受けてから手続きを進めます。
複数の遺言書がある場合は効力を確認
遺言書が複数存在する場合、日付が新しいものが優先されます。内容に矛盾がある場合は専門家に相談しましょう。
遺産分割協議は原則不要
遺言内容が明確であれば、相続人全員の合意なしに手続きが可能です。
司法書士や税理士と連携する
不動産登記や相続税申告の手続きが複雑でも、専門家と連携すれば安心して進められます。特に初めて遺言書に関わる場合は、書類の不備や手続きミスを防ぐために早めの相談が推奨されます。
関連記事
不動産を共有名義にするリスクと解決策 〜相続手続で揉めないために今できる準備とは〜②
商事信託と民事信託の違いを理解して、不動産相続を安全に進める方法|名古屋での実務事例も紹介②
【相続手続】行政書士ができること・できないこと|依頼メリットと費用を徹底解説①