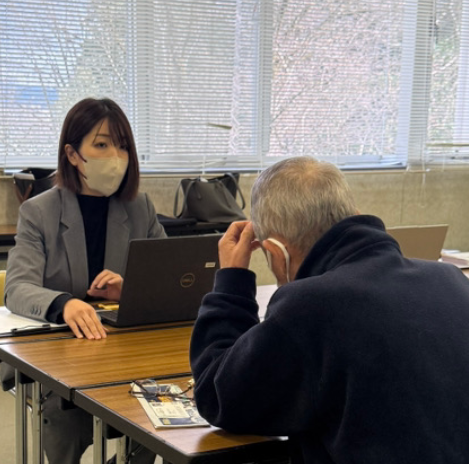
こんにちは!相続スタッフの伊藤です!
不動産を複数人で共有している場合、その中に所在がわからない共有者がいると、売却や活用が難しくなり、困ってしまうことがあります。
この記事では、そんな問題を解決するための新しい法律「民法第262条の2」について、わかりやすく解説します。
この制度を利用することで、所在不明の共有者の持分を取得し、不動産の活用や売却が可能になります。
この記事を読むことで、以下のことがわかります:
不動産の共有者の中に所在がわからない方がいてお困りの方は、ぜひ最後までお読みください!
「所在等不明共有者の持分取得制度」とは、不動産を共有している中で、他の共有者の所在がわからない場合に、裁判所の判断により、その共有者の持分を取得できる制度です。
この制度は、令和5年4月1日から施行され、共有不動産の活用や売却が進まない問題を解決するために導入されました。
共有不動産において、共有者の一人が所在不明になると、不動産の売却や活用が難しくなります。
このような問題を解決するために、裁判所の判断で所在不明共有者の持分を他の共有者が取得できるようになりました。
ある不動産を3人で共有していたところ、そのうちの1人が所在不明になり、売却が進まない状況になりました。
他の2人の共有者が裁判所に申し立てを行い、所在不明共有者の持分を取得することができました。
その後、不動産を無事に売却することができました。
「所在等不明共有者の持分取得制度」は、不動産の共有者の中に所在がわからない方がいる場合に、他の共有者がその持分を取得できる制度です。
この制度を利用することで、不動産の活用や売却が可能になります。
手続きには時間や費用がかかることがありますが、早めに対応することで、スムーズに問題を解決することができます。
お困りの際は、当事務所でもご相談を承っております。お気軽にお問い合わせください。
関連記事
相続登記の司法書士費用を徹底解説!名古屋・愛知で安心して依頼するための完全ガイド③
名古屋・愛知で不動産を相続された方へ:名義変更や費用、手続きの流れを徹底解説!②
【信託の委託者とは?】法人委託者の可能性と注意点を徹底解説|名古屋の相続・資産承継の実務から③