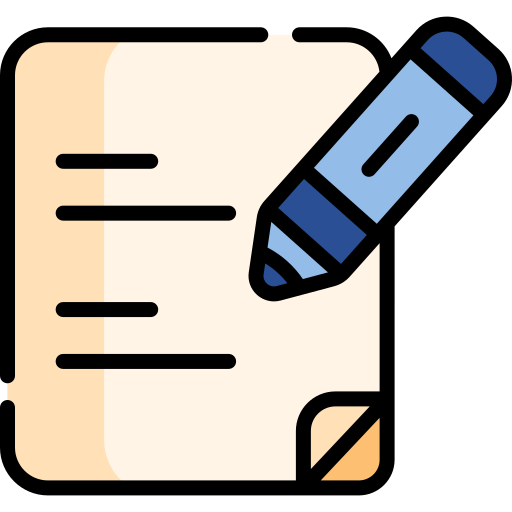
あいち相続ひろばの野々山です。
「遺言書が見つかったけれど、どのように相続手続きを進めればよいのか分からない」「遺言書の内容に従って不動産や預貯金の名義を変更したい」と悩んでいませんか。相続手続は、遺言の有無によって進め方が大きく変わり、専門知識がないまま進めると手続きの遅れや相続トラブルにつながることがあります。
本記事では、遺言書がある場合の相続手続の具体的な流れをわかりやすく解説します。遺言の種類、必要書類、司法書士や税理士との連携方法、注意点まで網羅しています。この記事を読むことで、手続きをスムーズに進めるための知識が身につき、安心して相続手続を進めることができます。特に、50〜70代で実家や自宅を相続予定の方、初めて遺言書に関わる方に向けた内容です。
遺言書に「遺言執行者」が指定されている場合、その人が相続手続の中心的な役割を担います。遺言執行者は、遺言書の内容に従って財産分配や名義変更、必要な申告を進める責任があります。
遺言執行者の主な役割
遺言書の内容確認と手続き全般の管理
相続人への通知や財産分割の調整
不動産登記や預貯金・証券の名義変更手続き
相続税申告のための財産目録作成
遺言執行者がいない場合は、相続人全員で遺産分割協議を行う必要があります。しかし、複数の相続人がいる場合や高齢者が含まれる場合、手続きが滞るリスクが高くなります。そのため、司法書士に依頼して遺言執行者として選任するケースもあります。
遺言書に従って財産を分割する際には、具体的な手順と確認ポイントがあります。
財産分割の手順
遺言書の内容を確認し、法的に有効かチェック
財産目録を作成(不動産・預貯金・有価証券・生命保険など)
相続人に内容を通知
必要に応じて専門家(司法書士・税理士)と相談
名義変更や相続税申告を進める
注意点
遺言書に「特定の財産を特定の相続人に譲る」と明記されている場合でも、手続き上の書類不足で滞ることがあります。
不動産は登記簿謄本に基づいて名義変更を行う必要があります。
金融資産は各銀行や証券会社の手続きルールに従うことが重要です。
これらを把握しておくことで、遺言書通りにスムーズに相続手続を進められます。
遺言書通りに財産を分割しても、相続税の申告が必要なケースがあります。特に不動産や高額預貯金が含まれる場合は、税理士と連携して正確に申告することが重要です。
主な軽減措置
配偶者の税額軽減(配偶者は1億6,000万円まで非課税)
小規模宅地等の特例(自宅や事業用不動産の評価額を最大80%減額可能)
相続税の申告期限(10か月以内)を守る
税理士と連携することで、軽減措置や特例を漏れなく適用でき、不要な税負担を避けられます。
遺言書があっても、手続き中にトラブルが起きることがあります。特に複数の相続人がいる場合や、財産の種類が多い場合は注意が必要です。
主なトラブル例
遺言書の内容に関する解釈の違い
財産の評価額を巡る争い
名義変更や税申告の遅延による利害不一致
防ぐための対策
遺言書の内容を相続人全員に事前に共有
財産目録を作成して明確化
手続きは司法書士・税理士と連携して進める
必要書類を事前に揃え、手続きを早めに開始する
これにより、遺言書の内容に沿った安全な相続が可能となります。
遺言がある場合でも、専門家に依頼することで手続きの安心感が大幅に向上します。
司法書士:不動産登記、遺産分割協議書作成、手続全般のサポート
税理士:相続税申告、財産評価、軽減措置の適用
両者連携:登記・税務・遺言内容を一貫して管理できる
相続人自身で行うよりも、ミスや手続きの滞りを防ぎ、相続人間のトラブルも減らせます。
遺言書の有効性を確認
財産目録を作成して整理
相続人全員に内容を通知
専門家と連携して手続きを進める
相続税の申告・軽減措置も漏れなく対応
これらを実行することで、遺言書に沿った円滑な相続手続が可能です。安心して財産分割や名義変更を進めるために、司法書士・税理士との連携を活用しましょう。
遺言書がある場合の相続手続は、不動産登記、預貯金・有価証券の名義変更、相続税申告など、多岐にわたります。遺言書の内容を正確に把握し、財産目録を作成して整理することが、手続きをスムーズに進める第一歩です。また、複雑な不動産や金融資産がある場合や相続人が複数いる場合は、司法書士や税理士と連携することで、書類不備や申告ミス、相続人間のトラブルを未然に防ぐことができます。
まずは遺言書の種類と内容を確認し、必要書類を揃えることから始めましょう。安心して遺言書通りの相続を進めるために、専門家と連携して手続きを進めることをおすすめします。これにより、遺言書の意向に沿った円滑で安心な相続が実現できます。
相続や不動産・家族信託で
お困りの方お気軽にご相談ください。
関連記事
相続登記を放置すると、実際どうなる?①
一宮市で“遠方でも安心”相続不動産の名義変更と売却をワンストップで進める方法|現地に行かず相続手続を完了する実務ガイド③
名古屋での相続登記費用はいくら?専門家依頼と自分でやる場合を徹底比較①【あいち相続ひろば】