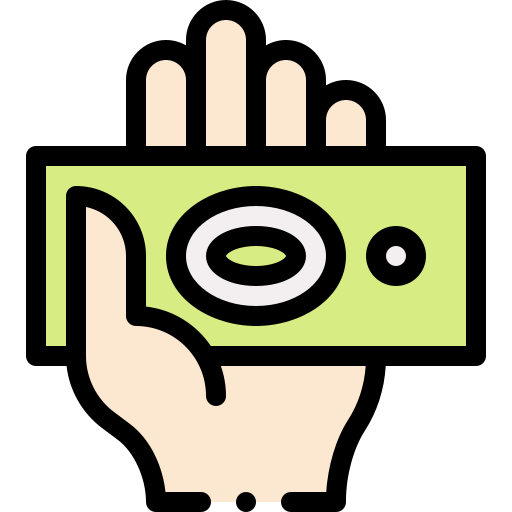
あいち相続ひろばの野々山です。
最近、「相続税の納税資金をどう準備するか」というご相談が増えています。
特に名古屋市内で不動産を複数所有している方の多くが、**「資産はあるけれど、現金が足りない」**という共通の悩みを抱えています。
相続税は原則として「現金一括納付」が求められるため、不動産が多い家庭では「納税資金の確保」が大きな課題になります。
そんなとき有効なのが、保険を活用した相続税対策です。保険を上手に使えば、相続発生時にスムーズに現金を確保し、納税や遺産分割を円滑に進めることができます。
この記事では、
相続税の納税資金を保険で準備する方法
不動産を多く持つ家庭での現金確保の実務
保険・贈与・信託を組み合わせた相続対策の具体例
を詳しく解説します。
「節税」だけでなく「実際に支払える仕組み」を整えたい方に、現場の実務経験をもとにわかりやすくお伝えします。
相続税の相談を受ける中で最も多いのが、**「資産はあるのに現金が足りない」**というケースです。
たとえば、名古屋市昭和区の山本さん(68歳)のように、自宅や賃貸不動産を所有している方は、帳簿上の資産額は高くても、実際に手元にある現金は限られています。
相続税は、相続発生から10か月以内に現金で納付しなければならないという厳しいルールがあります。
そのため、相続人は「不動産を売却して納税資金を作る」か、「借入れをして支払う」か、いずれかの方法を迫られることが多いのです。
しかし、現実には、
相続人間での遺産分割がまとまらない
不動産の売却がすぐに決まらない
不況で希望価格で売れない
といった事情により、期限内に現金を用意できないケースが少なくありません。
国税庁は、相続税の納付が難しい場合に「延納(分割払い)」や「物納(不動産で納税)」を認めています。
しかし、これらは“最終手段”であり、次のような条件が厳しく設けられています。
延納の場合:担保の提供や利子税の負担が必要(5年~20年の分割払い)
物納の場合:国が受け入れる資産条件(境界確定済み・共有でない・評価が安定している等)が必要
つまり、現実的には「保険などで現金を準備しておく」ことが最も確実な納税対策といえます。
相続税の支払いが滞ると、単なる税金問題にとどまらず、家族間の対立を生むこともあります。
たとえば、
「長男が自宅を相続するなら、長女が税金を多く払うのは不公平」
「不動産を売るのか、残すのか」で意見が割れる
「誰が借入れの保証人になるのか」で揉める
こうした争いは、“現金がないこと”が原因で発生する典型例です。
遺産が不動産中心の場合、「分けられない資産=分けにくい感情」へとつながり、結果的に相続が長期化することもあります。
名古屋市やその近郊(昭和区、瑞穂区、千種区、日進市など)では、
祖父母や両親から受け継いだ土地・賃貸物件を所有する「地主型相続」が多く見られます。
こうした方々は、
路線価が高く、相続税評価額が大きくなる
物件が複数あり、管理・分割が複雑
現金収入(賃料)はあるが、納税額に比べると小さい
という特徴があります。
このような場合、「節税」よりも「納税資金をどう準備するか」こそが最重要テーマになります。
相続税の納税資金対策として注目されているのが、生命保険の活用です。
保険金は、被相続人(亡くなった方)の死亡によって即座に現金化されるため、相続人が手続きに困ることなく納税資金を確保できます。
特に、「一時払い終身保険」や「相続対策保険」は、
契約者が被相続人
受取人が相続人
という設計にすることで、相続発生と同時に現金が入る仕組みを作ることができます。
さらに、死亡保険金には**「非課税枠(500万円×法定相続人の数)」**があり、節税効果も得られるため、
単なる納税準備ではなく、実務的な節税対策としても非常に有効です。
相続税対策は「相続が発生する前」に始めることが何より重要です。
特に保険を活用する場合、健康状態や年齢によって加入条件や保険料が大きく変わります。
「まだ元気だから大丈夫」と先延ばしにしてしまうと、
加入時期を逃してしまうことも珍しくありません。
つまり、相続税対策=生前の資金設計であり、
「節税」「納税」「分割」を一体的に考えることが、家族の未来を守る第一歩なのです。
相続や不動産・家族信託で
お困りの方お気軽にご相談ください。
関連記事
電話で安心!遺言の無料相談を活用する方法と名古屋の信頼窓口ガイド①
豊田市・岡崎市で農地を相続したら知っておきたい売却と転用の相続手続ガイド②
一宮市実家の相続で揉めないために ― 相続手続を見据えた遺言・家族信託・相続登記の実務ポイント①