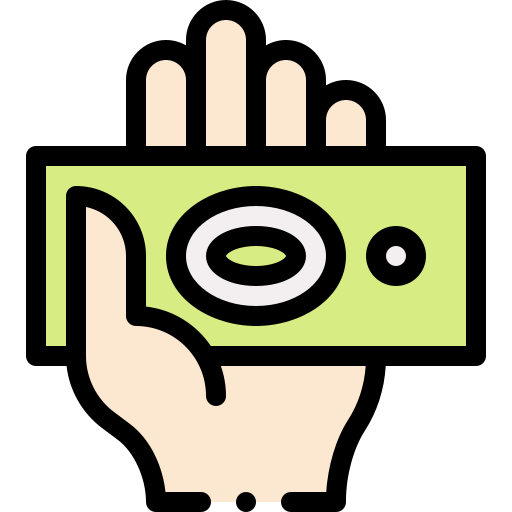
あいち相続ひろばの野々山です。
相続手続は、多くのご家庭にとって避けて通れない大きなテーマです。特に不動産や自社株などの分けにくい財産を多く持つ方にとって、円滑な遺産分割や相続税の納税資金の確保は大きな課題となります。そこで注目されているのが、生命保険を活用した相続対策です。
本記事では、保険が相続手続にどのように役立つのか、現金化のしやすさや受取人指定による公平性の確保、さらには節税効果まで幅広く解説します。さらに、元会社経営者である72歳男性をペルソナに設定し、実際の相続課題と解決策を具体的にご紹介。前編・中編・後編に分け、保険を使った実践的な相続対策をわかりやすく整理しました。
相続手続とは、被相続人(亡くなった方)の財産を法律に基づき承継するための一連の流れを指します。相続手続の対象となる財産は、不動産や現金、預貯金、株式などさまざまです。その中でも、不動産や自社株といった「分けにくい財産」を多く持つ場合、遺産分割や相続税の納税資金において大きな問題が生じやすくなります。
例えば、自宅や事業用の不動産が資産の大半を占めるケースでは、「相続税を払うための現金が不足してしまう」「兄弟間で不公平が生まれる」といった悩みが発生します。こうした課題を解決する有効な手段の一つが生命保険です。名古屋市や愛知県内でも、実際に保険を利用した相続対策を希望されるご相談は年々増えています。
生命保険の大きな特徴は、保険金が現金で支払われ、指定された受取人が直接受け取れるという点です。相続財産に含まれる現金や不動産とは異なり、保険金は相続財産とは切り離して扱われる場合が多く、スムーズに資金が確保できます。これにより、相続手続を進める際の「資金の準備」というハードルを大きく下げることが可能です。
特に、名古屋市のように不動産価格が高い地域では、自宅だけで数千万円から1億円を超えることも少なくありません。こうしたケースでは資産価値は大きいものの、現金化が難しく、納税資金をどう準備するかが最大の課題になります。
保険が相続において有効とされる理由を具体的に見ていきましょう。
現金化のしやすさ
相続税の納付期限は、相続開始(被相続人が亡くなった日)から10か月以内と定められています。不動産の売却には数か月以上かかることも珍しくありませんが、保険金は請求手続を行えば比較的早期に現金を受け取れます。
受取人を指定できる
保険契約では、保険金を受け取る人をあらかじめ指定することができます。遺産分割の対象となる財産を調整しにくい場合でも、保険金によって不公平感を緩和できるのです。
生活資金の確保
配偶者が遺された場合、年金収入だけでは生活に不安を感じるケースもあります。死亡保険金を受け取ることで、日常の生活費や医療費をカバーすることが可能です。
相続税の非課税枠を活用できる
生命保険の死亡保険金には「500万円 × 法定相続人の数」という非課税枠があります。例えば、配偶者と子ども2人が相続人であれば、合計1,500万円までが非課税です。この制度を活用すれば、相続税の負担を軽減できます。
納税資金の確保
相続税の納税は原則として現金一括払いです。延納や物納といった制度もありますが、手続きが複雑で認められない場合もあります。保険金なら確実に現金で納税資金を準備でき、相続人の負担を大きく減らせます。
今回のペルソナは、72歳の元会社経営者です。資産構成は以下の通りです。
自宅の土地・建物:1億円
預貯金:5,000万円
自社株:4,000万円
このケースでは、不動産と自社株といった分割しにくい資産が大部分を占めています。そのため、次のような課題が生じます。
長男に自社株を承継させたいが、相続税の納税資金が不足する
妻に十分な生活資金を残したい
長女には不公平感が残らないよう現金を残したい
名古屋市や愛知県でも、中小企業を経営してきた方に同様の悩みは多く見られます。特に「自社株を後継者に引き継がせたいが、納税資金をどう工面するか」という問題は深刻です。
こうした課題に対して有効なのが、一時払い終身保険や法人保険を活用した相続対策です。例えば、長女を保険金の受取人に指定すれば、長男が自社株を相続しても公平性を担保できます。また、一時払い終身保険で資金を確保しておけば、妻の生活費として活用できます。さらに法人契約の保険を利用すれば、納税資金の準備もスムーズに行えるのです。
相続や不動産・家族信託で
お困りの方お気軽にご相談ください。
関連記事
「兄弟の代表にされて困っている…」相続登記の義務化時代に知っておきたい手続きと解決策③【あいち相続ひろば】
【決定版】名古屋で土地の名義変更をお考えの方へ|相続登記から費用・手続きまでわかる完全ガイド③【あいち相続ひろば】
相続手続で失敗しないために知っておきたい遺言・信託・任意後見の組み合わせ方②