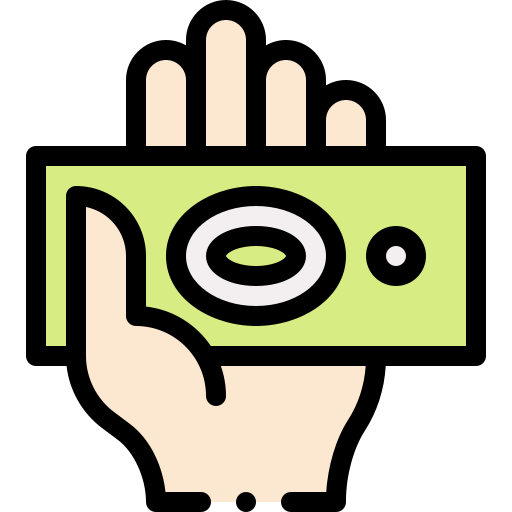
あいち相続ひろばの野々山です。
最近、「相続税の納税資金をどう準備するか」というご相談が増えています。
特に名古屋市内で不動産を複数所有している方の多くが、**「資産はあるけれど、現金が足りない」**という共通の悩みを抱えています。
相続税は原則として「現金一括納付」が求められるため、不動産が多い家庭では「納税資金の確保」が大きな課題になります。
そんなとき有効なのが、保険を活用した相続税対策です。保険を上手に使えば、相続発生時にスムーズに現金を確保し、納税や遺産分割を円滑に進めることができます。
この記事では、
相続税の納税資金を保険で準備する方法
不動産を多く持つ家庭での現金確保の実務
保険・贈与・信託を組み合わせた相続対策の具体例
を詳しく解説します。
「節税」だけでなく「実際に支払える仕組み」を整えたい方に、現場の実務経験をもとにわかりやすくお伝えします。
相続税納付資金を確保する方法として、保険だけでなく生前贈与も有効です。生前贈与とは、生きている間に財産を子どもや親族に渡すことで、相続税の課税対象を減らす手法です。
ポイントは年間110万円までの贈与税非課税枠を活用することです。
例えば、山本さんの場合、子ども2人に毎年110万円ずつ贈与すれば、年間合計220万円を非課税で移転できます。10年間続ければ2,200万円、20年間なら4,400万円を非課税で現金または預貯金として子どもに移すことが可能です。
メリット:納税資金として現金を子どもに直接渡せる
デメリット:一度贈与した資産は戻せない、生活資金を圧迫しないよう注意が必要
このように、計画的な生前贈与は現金不足リスクを大幅に軽減します。
もう一つの方法が、**家族信託(民事信託)**の活用です。信託とは、財産を「委託者(財産所有者)」が「受託者(信頼できる人や法人)」に託し、特定の「受益者(利益を受ける人)」に分配される仕組みです。
信託を活用すると以下の効果が期待できます。
財産管理が専門家に委任できる
相続発生後も、受託者がスムーズに資産を現金化して納税資金を確保
遺言書と異なり、柔軟に財産の分割・管理が可能
高齢の親の判断能力が低下しても、財産管理が続行される
名古屋市の山本さんは、自宅不動産を信託財産として設定し、受託者を信頼できる司法書士法人に指定しました。信託契約書には、以下の内容を盛り込みました。
相続税納税資金用に不動産を売却する手順
死亡保険金と組み合わせた現金化のタイミング
遺産分割のルール
これにより、不動産が多くても現金不足で相続人が困らない仕組みを事前に構築できます。
実際の現金確保対策は、複数の手段を組み合わせることで最大効果を発揮します。
保険:死亡時に即時現金化、納税資金を確保
生前贈与:長期的に子どもに現金を分散、相続税軽減
信託:不動産など流動性が低い資産を管理・現金化、相続手続をスムーズに
名古屋市の山本さんの場合の組み合わせ例:
自宅・賃貸不動産:信託に設定し、受託者が管理
相続税納付分:一時払い終身保険で1,000万円確保
子どもへの生前贈与:年間110万円×2人、10年間で2,200万円移転
これにより、相続税の納税資金を十分に確保しつつ、子どもたちに過剰な負担をかけない体制が整います。
税務署との調整
贈与税や信託契約の内容によっては、税務署が否認するリスクもあります。事前に税理士に相談して設計することが重要です。
専門家の連携
保険会社、税理士、司法書士を横断して、納税・遺産分割・信託運用の全体像を把握する
名古屋市・愛知県内での実務経験がある専門家が安心です
書類整備
保険契約書、信託契約書、贈与契約書などは最新状態で保管
相続手続をワンストップで任せられる体制を整備
保険・信託・生前贈与を組み合わせることで、資産はあるのに現金が足りないという相続リスクを回避できます。さらに、手続や分配を事前に設計することで、子どもたちの争いを防ぎ、安心して老後を過ごせます。
次のステップは、名古屋市や愛知県で実績のある専門家チームに相談し、具体的な設計を進めることです。これにより、相続発生後の現金確保と手続のスムーズ化を両立できます。
あいち相続ひろばの野々山です。本記事では、相続税対策としての保険活用や現金確保の実務、さらに生前贈与や信託を組み合わせた戦略について詳しく解説しました。
不動産など現金化しにくい資産が多い場合でも、一時払い終身保険や相続対策保険を活用すれば、納税資金を確実に確保できます。また、年間110万円までの非課税枠を活用した生前贈与や、家族信託による資産管理を組み合わせることで、子どもたちに過剰な負担をかけず、相続手続をスムーズに進めることが可能です。
名古屋市・愛知県内で実績のある司法書士や税理士、保険コンサルタントと連携すれば、納税資金の準備から遺産分割までワンストップで安心して任せられます。将来の相続トラブルや資金不足を回避したい方は、今のうちに専門家に相談して具体的なプランを立てることをおすすめします。
相続や不動産・家族信託で
お困りの方お気軽にご相談ください。
関連記事
「高齢単身者の一宮市実家整理 ― 遺産分割協議書作成から不動産売却まで安心して進める方法」①
刈谷市の単身・高齢者が選ぶ終活対策とは 身元保証と相続手続を同時に考える、後悔しない安心設計ガイド③
家族がもめない相続対策とは|元経営者のための遺言と事業承継の進め方【名古屋版】① 【あいち相続ひろば】